 柧恄弇 儗僕儏儊俀
柧恄弇 儗僕儏儊俀
|
乽峕屗怘暥壔偲峕屗暥寍乿丒戞俀夞
丂丂丂丂丂丂峕屗偺堛怘摨尮
丂丂丂丂丂乣塰梴偲梴惗乣
丂丂丂2015擭6寧17擔丂埨摗桪堦榊
|
|
仧島嵗偺庯巪丂 |
|
丂擔杮暥壔偺尮棳偼峕屗帪戙偵偝偐偺傏傞偲尵偭偰傕夁尵偱偼側偄偱偟傛偆丅崱婜偼怘偲暥寍傪僥乕儅偲偟偨儈僯島嵗偵壛偊偰丄僞僀僩儖偵偪側傫偩僎僗僩偲偺懳択傪捠偠丄奆偝傫傪枺椡偁傆傟傞峕屗暥壔偺悽奅偵偄偞側偄傑偡丅
|
|
仧偼偠傔偵丂 |
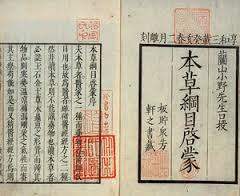 丂峕屗帪戙偼丄寬峃傊偺娭怱偺崅偝偐傜堛栻昳偺廀梫偑崅傑偭偨帪戙偱偟偨丅抦傜傟偞傞峕屗偺寬峃嶻嬈偺揥奐傪夝愢偟傑偡丅
丂峕屗帪戙偼丄寬峃傊偺娭怱偺崅偝偐傜堛栻昳偺廀梫偑崅傑偭偨帪戙偱偟偨丅抦傜傟偞傞峕屗偺寬峃嶻嬈偺揥奐傪夝愢偟傑偡丅
|
|
侾丏峕屗偺杮憪妛 |
乮侾乯堛怘摨尮巚憐偺朑夎
拞崙偱娍偺帪戙偵杮憪彂抋惗/崙壠偑堛栻帠嬈偵椡傪擖傟傞/棩椷崙壠偱傕揟栻椌愝抲/拞崙堛彂傪嶲峫偵揤尦俆擭乮982乯亀堛怱曽亁嶌惉/棷妛憁傪捠偠堛妛忣曬揱攄/堛彂堛栻昳偑棳擖/搶傾僕傾悽奅偼恎搚晄擇乮恎懱偲帺慠偼堦懱乯偺巚憐/堛怘摨尮丒栻怘婣堦
乮俀乯杮憪妛偺戜摢
拞崙桼棃偺杮憪妛偼丄栻憪傪偼偠傔栻暔偲偟偰偺梡傪側偡摦怉峼暔偺抦幆偵娭偡傞妛栤/栻岠偺帇揰偐傜暘椶仺攷暔妛傊/宑挿12擭乮1607乯偵棝帪捒偺亀杮憪峧栚亁偑擔杮傊/帺慠暔傪16晹丄奺晹傪60椶偵暘椶/尦榎10擭乮1697乯偵恖尒昁戝偺亀杮挬怘娪亁姧峴乣擔杮撈帺偺怘暔傕壛偊傜傟傞/怘暔杮憪偺尋媶偑恑揥仺堛怘摨尮/曮塱俇擭乮1709乯偵奓尨塿尙偺亀戝榓杮憪亁姧峴丅1366庬偺帺慠暔傪夝愢乣擔杮屌桳偺358庬娷傓
乮俁乯暔嶻挷嵏偲栻昳夛
尦暥俁擭乮1738乯偵壛夑斔巟墖偺傕偲堫惗庒悈偺亀彅暔椶嶽亁姰惉/枊晎彅斔偵傛傞暔嶻挷嵏帠嬈偑妶敪壔乣怋嶻嫽嬈惌嶔偺婎慴帒椏/暔嶻挷嵏丒廂廤丒嵧攟偺偨傔杮憪壠傪妶梡/嫕榓俁擭乮1803乯傛傝堛妛娰嫵庼彫栰棖嶳偺亀杮憪峧栚孾栔亁48姫姧峴奐巒乣杮憪妛偺廤戝惉/杮憪尋媶偺恑揥傪庴偗忣曬岎姺傪栚巜偡揥帵夛乮杮憪夛丒栻昳夛丒暔嶻夛乯偑奺抧偱奐嵜/曮楋俈擭乮1757乯偵暯夑尮撪偑搾搰偱嵟弶偺栻昳夛/杮憪妛偼攷暔妛偵敪揥
乮係乯媬峳杮憪偺搊応
峕屗偺婹閇乣嫢嶌丒嵭奞偵傛傝昿敪/婹閇帪偺怘梡怉暔乮媬峳怘暔乯偺嵧攟朄傪柉娫偵採帵/嫕曐婹閇帪偺塽昦棳峴傪庴偗丄枊堛朷寧嶰塸丒扥塇惓攲偑怘暔偺撆偵偁偨偭偨帪偺懳張椕朄傪奺懞偵廃抦/嫕曐20擭乮1735乯偵 惵栘崺梲偑亀斪彄峫亁挊偡/揤柧偺婹閇屻丄媬峳彂偑杮奿揑偵弌斉斝晍乣嵧攟丒挷棟朄傪杮憪彂傗擾彂偺抦幆傪嬱巊偟偰夝愢 惵栘崺梲偑亀斪彄峫亁挊偡/揤柧偺婹閇屻丄媬峳彂偑杮奿揑偵弌斉斝晍乣嵧攟丒挷棟朄傪杮憪彂傗擾彂偺抦幆傪嬱巊偟偰夝愢
|
|
俀丏峕屗偺栻 |
乮侾乯枊晎偺栻憪惌嶔
揤暥丒婥徾丒抧棟側偳幚妛傪廳傫偠偨彨孯媑廆/堛妛丒栻妛彂傪嵗塃偵丅帺傜惢栻/杮憪妛幰傪搊梡偟丄栻憪尒暘偺偨傔慡崙偵攈尛/彅斔偺栻憪挷嵏傕妶敪壔/恖嶲偺崙嶻壔惌嶔乣挬慛恖嶲偑巗応撈愯/枊堛揷懞棔悈偑栻梡恖嶲偺嵧攟偲惢栻壔偺拞怱偵
乮俀乯栻墍偺惍旛
嫕曐俆擭乮1720乯偵嬵応栻墍奐愝/梻俇擭乮1721乯偵彫愇愳栻墍偑戝奼挘乮4800捸仺44800捸乯/俈擭乮1722乯偵壓憤彫嬥栰偵30枩捸偺栻墍奐愝/慡崙奺抧偵栻墍奐愝乣恖嶲側偳傪戝乆揑偵嵧攟偟丄彅斔偵庬傪梌偊傞/彫愇愳栻墍偱娒潋傪帋嶌/梴惗強愝抲
乮俁乯峕屗偺栻庬壆
峕屗廫慻栤壆偵栻庬揦慻/杮挰栻庬栤壆拠娫寢惉/嫕曐俈擭偵栻昳偺昳幙丒壙奿娗棟丄棳捠検挷嵏傪栚揑偲偡傞榓栻夵夛強愝抲/栤壆傪夘偟偨栻庬摑惂/嶳搶嫗揱偺乽撉彂娵乿/嬋掄攏嬚偺惢栻斕攧/幃掄嶰攏偺乽墑庻扥乿/壔徬悈乽峕屗偺悈乿斕攧
|
|
俁丏梴惗偺棳峴 |
乮侾乯梴惗杮偺棳峴
梴惗偺堄枴/拞悽擔杮偱偼栻偵傛傞梴惗偲偄偆敪憐偑嫮偄/峕屗帪戙偵怘偲恎懱偺娭學傪惛恄柺偐傜僐儞僩儘乕儖偟偰寬峃偺堐帩傪偼偐傞梴惗榑偑搊応/惓摽俁擭乮1713乯偵奓尨塿尙偺亀梴惗孭亁姧峴/怘傋夁偓丒堸傒夁偓傪夲傔傞乣帺慠帯桙椡傊偺婜懸/壠掚堛妛彂丒寬峃夝愢彂偵偁偨傞梴惗彂偑懡悢弌斉乣戄杮壆傪捠偠偰棳晍
乮俀乯峕屗偺棳峴昦偲梴惗強
晽幾丒杻怾丒醰釋丒媟婥丒僐儗儔棳峴/嫕曐15擭乮1730乯偵枊堛椦椙揔偨偪偵傑偲傔偝偣偨亀晛媦椶曽亁姧峴/挰恖丒擾柉栤傢偢崲媷柉偵岦偗偰嶳栰偱摼傗偡偄栻曽傪採帵/幘昦偺嵺偺懳張椕朄傕採帵/棳峴昦帪偵壓憌柉傊屼媬暷丒慘偺巟媼
乮俁乯梴惗強偺愝抲乮恾嘍乯
嫕曐俈擭偵彫愇愳栻墍撪偵梴惗強愝抲/巤椕丒擖強懳徾偼昻崲偱栻偑暈梡偱偒側偄幰丄撈恎偺偨傔昦婥偵側偭偰傕娕昦恖偑偄側偄/掕堳117柤
|
|
係丏惣梞堛妛偲塰梴 |
乮侾乯娍曽堛偲棖曽堛
娍曽堛偺夊忛堛妛娰偲墱堛巘懡婭巵/棖妛偺戜摢偲僔乕儃儖僩偺柭戧弇/庬摋強偺愝抲/棖曽堛偺墱堛巘搊梡/惣梞堛妛強偺愝抲

乮俀乯寬峃偺抋惗
晉崙嫮暫偲暥柧奐壔/暉戲桜媑偨偪偵傛傞惣梞暥柧偺孾栔/暷怘偐傜擏怘傊/媿擕偺晛媦/寬峃偲塰梴/塹惗惂搙偺妋棫偲孯戉/岤惗徣偺抋惗
|